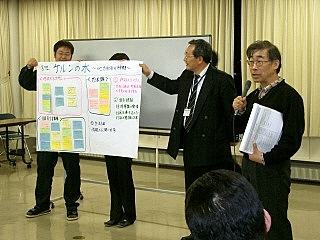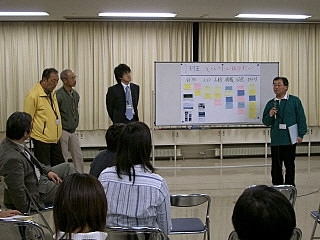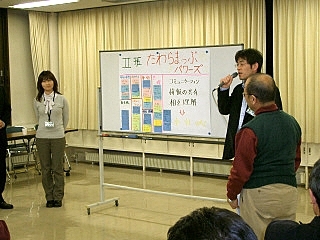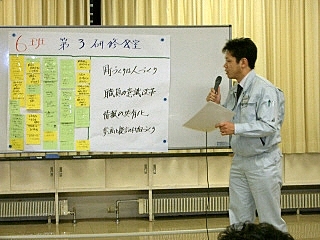第6回「パートナーシップで進めるまちづくり」町民会議
日時
平成18年4月18日(火)19:00~21:20
場所
中標津町役場301号会議室
出席者
38名(町民委員19名、プラネット18名、ファシリテーター:東田秀美氏)
会議次第
配布資料
- 第5回会議結果
結果概要
議題に入る前に事務局より連絡
- 4月1日の人事異動に伴い、プラネットメンバーの所属の変更と事務局の異動がありましたので新しい委員名簿を配りました。
- 平成18年度のパートナーシップ推進事業の予算について報告しました。
- 北海道の地域力形成実践事業の内容を説明し、この「パートナーシップで進めるまちづくり用民会議」をモデル地区に要望し北海道の協力をいただきながら、今後会議を進めることを了承していただきました。
- 「パートナーシップで進めるまちづくり町民会議」について、町民の方から質問が届き、質問内容を報告、後日事務局が面談の上説明することになりました。(質問と回答は下記リンクを参照)
- 質問と回答(PDF形式:22KB)
1、第5回町民会議の確認(振り返り)会議結果について
事前に配布しておりますので説明は省略させていただきました。
2、グループワーク発表
各班のラベルワークの結果を発表しました。
- 配布資料その2(PDF形式:76KB)
各班のラベルワーク結果発表
◎3班(班名=ケルンの森 ~地方自治の神髄~)
発表者 猿渡委員・櫻田委員
町内会・商工会・色々な組織から集まってくる。それらを1つにまとめるのが町民会議という大きな組織であると思う。
発表者 猿渡委員・櫻田委員
- 行政のシステム
- 個別問題
- 方法論
町内会・商工会・色々な組織から集まってくる。それらを1つにまとめるのが町民会議という大きな組織であると思う。
◎4班(班名=風のたより!)
発表者 及川委員
役場にポイントをしぼった。開拓してほしい、役場はサービス業という事を常に意識してほしい。
発表者 及川委員
- 情報発信の整理
- 親しみのある役場(使いやすい、便利な)
- 意見交換の場があり、反応のある対応
役場にポイントをしぼった。開拓してほしい、役場はサービス業という事を常に意識してほしい。
◎5班(班名=しらかば)
発表者 眞野委員
町全体が農業主体産業ということで、今回の会議で牛乳が出ているが、牛乳消費拡大に協力している。自発的に町の産業を応援して行かなければならないという思いだとか、そういうような取り組みをしていくこと自体、もう協働なのかなと思いました。
発表者 眞野委員
- 情報が公開され、共有し、話し合い、川野流れのように一団、一丸となる。
- 対等な関係
- 楽しく活気ある暮らし ~支えあう暮らし~
町全体が農業主体産業ということで、今回の会議で牛乳が出ているが、牛乳消費拡大に協力している。自発的に町の産業を応援して行かなければならないという思いだとか、そういうような取り組みをしていくこと自体、もう協働なのかなと思いました。
◎2班(班名=たわらまっぷパワーズ)
発表者 天野委員・阿部委員
発表者 天野委員・阿部委員
- コミュニケーション
- 情報の共有
- 相互理解
コメント:
◎6班(班名=第3研修室)
発表者 下村委員
全体像が見えない中、パートナーシップを進める上での課題だとか方向性についてと意見がほとんどでした。以上のキーワードが出来るようになってパートナーシップにつながるのではないか、ということでまとめました。
発表者 下村委員
- まちづくりは人づくり
- 情報の意識改革
- 参画と提言の仕組みづくり
全体像が見えない中、パートナーシップを進める上での課題だとか方向性についてと意見がほとんどでした。以上のキーワードが出来るようになってパートナーシップにつながるのではないか、ということでまとめました。
委員の皆さんにラベルワークを行って頂いた結果を、ファシリテーターの東田さんにまとめて頂きました。(まとめは下記リンクを参照)
- パートナーシップを進めるための大まかな課題整理(PDF形式:24KB)
ファシリテーター 東田

各班から発表して頂いた中で、共通するキーワードみたいなものが出てきていると思います。
例えば、情報・共有・公開・対等な関係を築ける場、意見交換の場がほしい・接点がほしい・民意をもうちょっと作ってほしいというような事、いくつかキーワードになってきた言葉があると思います。
中標津町の自然や暮らしという事で自然環境、産業これが農業ですとか商業、他にもありますが、それともう1つの市街地、こういうもので中標津町が形成されているのかなと私自身は思っています。その中で皆さんは暮らしている。
今出して頂いた色々な課題を3つの枠組みに分けてみました。
右側は主に町民の皆さんの課題で、左側は主に役場側・行政側の課題で、真ん中が相互理解するための課題です。
主に町民側の方の課題として出ていたのは、町民の自主性の問題、今回パートナーシップについてですね、自主性でないか人材育成が大事というようなこと、この中で奉仕の心・ボランティアの活性化・自主的な参加を保障する。ようは誰でもかれでも入れではなくて、入りたい人が入る。というようなキーワードが出たと思います。
役場側の課題は、職員の意識改革、町民の自主性・人材育成に対応しているように、今度は職員の方の意識改革・人材育成という言葉が随分出ていました。
これはコミュニケーション能力が悪い、もっとそれを良くしてほしい、親しみのある役場を作ってほしい、個別の具体的なものだとサービス意識を持ってほしい、配置を分かり易くしてほしい、育成だとか簡単に出来るようなところ1番ベーシックなものです。
その上に仕組みの問題で、行政のシステム・仕組みの問題、課題としてあったのが参画・提言の仕組みがほしい・一町民でも意見を述べられる・計画段階から参加したい・窓口の必要性・総合案内所・手続きを簡単に・バランスシートというような、どちらかというと仕組みそのものをある程度変えればどうにかなる、というようなことです。
でもこれは、これだけを変えるんじゃなくて、あくまで意識を改革したり、人材をきちんと育成したり、コミュニケーションがあるということがベースになっているということの考え方の上に乗っています。
町民側の皆さんの課題として、今発表を聞いて思ったのは、やっていくこと・実行すること・自主性・自発的に取り組む、それの操作プランだとか手立てみたいなこと、発表の中では、農協さんの話だとか様々な活動をしている方からの話として実際ありました。
役場の課題と町民の課題を結びつける真ん中の部分です。相互理解のための課題で、1番数多く出てきたのが情報公開、この情報についても色々課題というか出てきて発信の整理をして、それから公開の方法を考えて、そしてそれを共有する事が大事ということが出てきたと思います。
その方法については、例えば広報誌のやり方・予算についても分からない・納税額を知らせた方がいい・情報の入手の方法・周知の手段が今は今ひとつ、経緯がわからない、2階の印刷室を利用して色々な活動をする、情報を発信している様々な事、この発信の整理と公開と共有の方法論が、ほとんど皆さんの班から上がってきたものだと思います。
もう1つ出てきたのが、対等な関係の場づくりで、今回の町民会議をレベルアップした、提言・訪問の機関として、これをレベルアップしていくというような意見だとか、意見交換の場が無い、出前講座を活用したほうが良いというような対等の関係をつくる意見交換の場、もしかしたら町民会議であったり、それを発展させる形であったり、色々な共有の場がほしい、でもそれは情報を共有した上であり、行政の課題と町民の課題をつなぐものがこの真ん中の相互理解の課題だと思います。
皆さんの方から例えば公園の管理のこと、病院のこと、市街地活性化・ごみの問題・教育というような色んな個別の話題・課題が出てきたと思います。
今、パートナーシップの町民会議はその個別の課題について話し合うのではなく、その個別の課題の何をクリアすればその個別の課題への対応がしやすくなるか、というような事を考えた方がいいと思います。
それは、目的を共有して個別の課題に対応するために、例えば祭りとかイベントの共催の事が色々皆さんから出ました。
その共催の仕組み・手順を簡単にすることが出来ないだろうか、個別の課題の検討会議を1個1個設置したらどうかというようなことも随分意見としてありましたし、検討に対してどうかしてほしい、審議したい、そんな感じで出ていました。
また、何故協働するのかパートナーシップってどこで必要なのかというような事を話し合う場だとか、全部に対してパートナーシップを使う必要はないと思いますけど、何に対してどういう風に使っていくかっていうことを検討したり、皆で話し合ったりする場っていうのは必要なのかな、それがあって初めて個別の課題の対応が簡単に出来ていくというようなイメージがあります。
これは私が今日皆さんのお話聞いて取りまとめた図です。
特に今回パートナーシップで進めるこのまちづくり町民会議は1番最初に話し合わなければならない、重要だと思う部分は相互理解のための課題かなと、私自身は思います。次の役場の課題で町民の課題が第3番というふうに私自身は思うんですが、皆さんはどのように思われるかという討議を次回に行いたいと思います。
パートナーシップで進める町民会議は、どこで話し合うの、どの方法を話し合うの、どこの内容を話し合うのっていう時に、優先順位1番、相互理解のための課題、2番は役場の課題、3番は町民の課題、1つ1つの方法論が出来上がれば仕組みのアイデアが出て、こういう風にしたい、こういう風にしていこうみたいな、アイデアの具体的な事、そしてそれを実行できれば、かなり行政と町民のコミュニケーションは取れると思います。
ところが、行政の仕組みをパートナーシップで進めるには、まだまだ足りない要素が沢山あるので、ここをもうちょっと具体的に話し合ってもらって、出来る事、出来ない事を整理しましょう。
意識改革という言葉は非常に簡単ですけれども、意識改革をしてもらう方法論、今まで簡単に意識を変えてください、変えてくださいと言っても、今まで変わってきていないのです。
変わってきていないから多分、今の現状があると思います。
私自身が普段、他の時にご提案させて頂いているのは、意識を改革するためにどうするか、方法論が大事です。
役場の人は事務職しかやったことがないので、コミュニケーション能力が無い、勉強したことが無い、それを必要と思っていない。
1人2人が講座に通って他の人に教えるようになって、意識だけでかわらない部分も能力としてそれを身につけてもらう、意識だけの事ではないはずです。
具体的な仕組み・中身だとか職員研修の方法論、あり方みたいなところも変えれば、お金をかけなくても行政の課題は少し変わってきます。
今日まで、話し合い、意見を1個1個出して頂いて、ワベルワークを実施しました。
初めてじゃなかった人もいると思いますし、初めての方もいると思いますけ ど、まず話し合うことと共有の課題、同じような言葉が結果的に出てきたと思います。それを具体化するような町民会議にしていきたいと思います。
例えば、情報・共有・公開・対等な関係を築ける場、意見交換の場がほしい・接点がほしい・民意をもうちょっと作ってほしいというような事、いくつかキーワードになってきた言葉があると思います。
中標津町の自然や暮らしという事で自然環境、産業これが農業ですとか商業、他にもありますが、それともう1つの市街地、こういうもので中標津町が形成されているのかなと私自身は思っています。その中で皆さんは暮らしている。
今出して頂いた色々な課題を3つの枠組みに分けてみました。
右側は主に町民の皆さんの課題で、左側は主に役場側・行政側の課題で、真ん中が相互理解するための課題です。
主に町民側の方の課題として出ていたのは、町民の自主性の問題、今回パートナーシップについてですね、自主性でないか人材育成が大事というようなこと、この中で奉仕の心・ボランティアの活性化・自主的な参加を保障する。ようは誰でもかれでも入れではなくて、入りたい人が入る。というようなキーワードが出たと思います。
役場側の課題は、職員の意識改革、町民の自主性・人材育成に対応しているように、今度は職員の方の意識改革・人材育成という言葉が随分出ていました。
これはコミュニケーション能力が悪い、もっとそれを良くしてほしい、親しみのある役場を作ってほしい、個別の具体的なものだとサービス意識を持ってほしい、配置を分かり易くしてほしい、育成だとか簡単に出来るようなところ1番ベーシックなものです。
その上に仕組みの問題で、行政のシステム・仕組みの問題、課題としてあったのが参画・提言の仕組みがほしい・一町民でも意見を述べられる・計画段階から参加したい・窓口の必要性・総合案内所・手続きを簡単に・バランスシートというような、どちらかというと仕組みそのものをある程度変えればどうにかなる、というようなことです。
でもこれは、これだけを変えるんじゃなくて、あくまで意識を改革したり、人材をきちんと育成したり、コミュニケーションがあるということがベースになっているということの考え方の上に乗っています。
町民側の皆さんの課題として、今発表を聞いて思ったのは、やっていくこと・実行すること・自主性・自発的に取り組む、それの操作プランだとか手立てみたいなこと、発表の中では、農協さんの話だとか様々な活動をしている方からの話として実際ありました。
役場の課題と町民の課題を結びつける真ん中の部分です。相互理解のための課題で、1番数多く出てきたのが情報公開、この情報についても色々課題というか出てきて発信の整理をして、それから公開の方法を考えて、そしてそれを共有する事が大事ということが出てきたと思います。
その方法については、例えば広報誌のやり方・予算についても分からない・納税額を知らせた方がいい・情報の入手の方法・周知の手段が今は今ひとつ、経緯がわからない、2階の印刷室を利用して色々な活動をする、情報を発信している様々な事、この発信の整理と公開と共有の方法論が、ほとんど皆さんの班から上がってきたものだと思います。
もう1つ出てきたのが、対等な関係の場づくりで、今回の町民会議をレベルアップした、提言・訪問の機関として、これをレベルアップしていくというような意見だとか、意見交換の場が無い、出前講座を活用したほうが良いというような対等の関係をつくる意見交換の場、もしかしたら町民会議であったり、それを発展させる形であったり、色々な共有の場がほしい、でもそれは情報を共有した上であり、行政の課題と町民の課題をつなぐものがこの真ん中の相互理解の課題だと思います。
皆さんの方から例えば公園の管理のこと、病院のこと、市街地活性化・ごみの問題・教育というような色んな個別の話題・課題が出てきたと思います。
今、パートナーシップの町民会議はその個別の課題について話し合うのではなく、その個別の課題の何をクリアすればその個別の課題への対応がしやすくなるか、というような事を考えた方がいいと思います。
それは、目的を共有して個別の課題に対応するために、例えば祭りとかイベントの共催の事が色々皆さんから出ました。
その共催の仕組み・手順を簡単にすることが出来ないだろうか、個別の課題の検討会議を1個1個設置したらどうかというようなことも随分意見としてありましたし、検討に対してどうかしてほしい、審議したい、そんな感じで出ていました。
また、何故協働するのかパートナーシップってどこで必要なのかというような事を話し合う場だとか、全部に対してパートナーシップを使う必要はないと思いますけど、何に対してどういう風に使っていくかっていうことを検討したり、皆で話し合ったりする場っていうのは必要なのかな、それがあって初めて個別の課題の対応が簡単に出来ていくというようなイメージがあります。
これは私が今日皆さんのお話聞いて取りまとめた図です。
特に今回パートナーシップで進めるこのまちづくり町民会議は1番最初に話し合わなければならない、重要だと思う部分は相互理解のための課題かなと、私自身は思います。次の役場の課題で町民の課題が第3番というふうに私自身は思うんですが、皆さんはどのように思われるかという討議を次回に行いたいと思います。
パートナーシップで進める町民会議は、どこで話し合うの、どの方法を話し合うの、どこの内容を話し合うのっていう時に、優先順位1番、相互理解のための課題、2番は役場の課題、3番は町民の課題、1つ1つの方法論が出来上がれば仕組みのアイデアが出て、こういう風にしたい、こういう風にしていこうみたいな、アイデアの具体的な事、そしてそれを実行できれば、かなり行政と町民のコミュニケーションは取れると思います。
ところが、行政の仕組みをパートナーシップで進めるには、まだまだ足りない要素が沢山あるので、ここをもうちょっと具体的に話し合ってもらって、出来る事、出来ない事を整理しましょう。
意識改革という言葉は非常に簡単ですけれども、意識改革をしてもらう方法論、今まで簡単に意識を変えてください、変えてくださいと言っても、今まで変わってきていないのです。
変わってきていないから多分、今の現状があると思います。
私自身が普段、他の時にご提案させて頂いているのは、意識を改革するためにどうするか、方法論が大事です。
役場の人は事務職しかやったことがないので、コミュニケーション能力が無い、勉強したことが無い、それを必要と思っていない。
1人2人が講座に通って他の人に教えるようになって、意識だけでかわらない部分も能力としてそれを身につけてもらう、意識だけの事ではないはずです。
具体的な仕組み・中身だとか職員研修の方法論、あり方みたいなところも変えれば、お金をかけなくても行政の課題は少し変わってきます。
今日まで、話し合い、意見を1個1個出して頂いて、ワベルワークを実施しました。
初めてじゃなかった人もいると思いますし、初めての方もいると思いますけ ど、まず話し合うことと共有の課題、同じような言葉が結果的に出てきたと思います。それを具体化するような町民会議にしていきたいと思います。

委員から出された意見
- 町民会議の名前を変えたほうが良いという意見が以前にもありましたが、このまま「パートナーシップで進めるまちづくり町民会議」で進めることになりました。
- パートナーシップの定義は、個人個人の経験などで、価値観が違うので同じくする必要はなく、定義づけしなければならないものではないと思う。
- パートナーとは完全にくっついた状態で、パートナーでいこうとする状態をパートナーシップというのではないか、町民会議を進めていくうちに見えてくるのではないかと思う。
次回は、グループ分けした内容の現状を全体討議し、更にもう少し詳しくグループ討議で話し合い全体討議に反映させて、パートナーシップという言葉の持つ意味、それぞれの個別の仕組みをどう変えていけばよいか、を話し合います。
このページの情報に関するお問い合わせ先
政策推進課協働推進係 電話番号:0153-74-0728FAX:0153-73-5333
政策推進課協働推進係 電話番号:0153-74-0728FAX:0153-73-5333